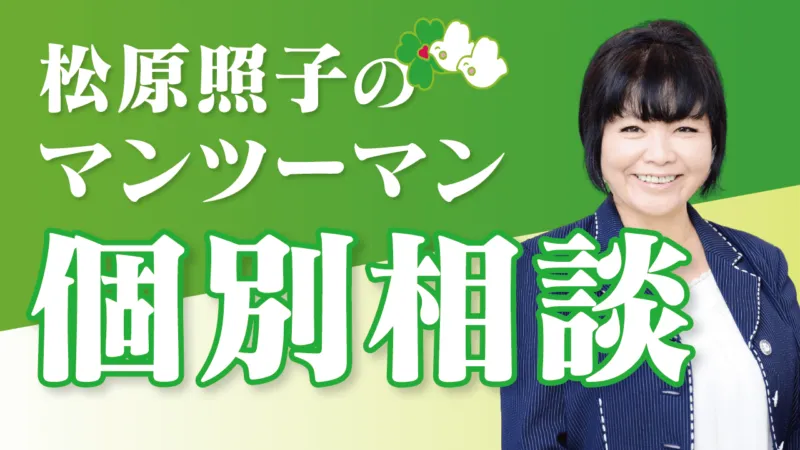お寺にお参りに行かれる時、仏様に手を合わせますが、あなたは仏像の種類と役割をご存じですか?
初めはお釈迦様の像だけだったのが、お釈迦様以外にも仏様が存在するという考え方が出て、如来になる前段階の菩薩像が登場しました。
仏教の歴史が続くにつれて、仏像の数も増えていきました。
奈良・東大寺の「盧舎那仏坐像(るしゃなぶつざぞう)」と書いても、分からない方もおられると思いますが、奈良の大仏様のことです。
銅造りで、像の高さ約15メートルの国宝です。
仏様の役割を知っていれば、これからお寺に参いられる時、仏様からパワーをいただけますからね。